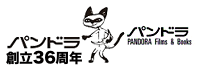|
V.E.フランクルの『夜と霧』の読書体験はまさに「衝撃」だった。人間の極限悪を告発する記録ではあったが、その「衝撃」はナチズムの残酷、非人間的なシステムに対してではなく、人間という存在それ自体の不気味さを明晰な文章で綴った心理学者フランクルの視座、ゆらぎのない冷徹にあったように思う。
餓え疲労困憊し、恥の概念も剥ぎ取られ、突然の自死が何時、訪れるかも知れないという極限状況のなかでも自己と他者に向けた静かな視座を確保・維持しつづけたフランクルという人の存在そのものが「衝撃」であったのだと思う。『夜と霧』を読んだのは10代の後半だったと思うが、その読後感はいまだに生きている。
以来、ナチ強制収容所の実態を綴った本と幾度も出会ってきた。その多くが地獄を奇跡的に生き延びた体験者の報告・記録であった。そうした記録を読めば読むほど、生還した人たちは、それだけで奇跡の偉人のように思えてくる。そうした記録は、繰り返し映像化される劇映画に深い陰影を与えつづけた。人間はどこまで残酷になれるのか、どこまで苦痛と恥辱に耐えられる存在であるのかを推量する目安まで強制されるような、曰く言いがたい不快感、と同時に人間存在に対する信頼感もまた受け取っているのだ。それでなければ繰り返し、極限悪を読み返す気は起こらない。
本書『ピンク・トライアングルの男たち』も深甚な課題を抱えて筆者の前に現われた。近年では2004年秋、母親が強制収容所のメ有能モな看守であったというヘルガ・シュナイダーが書き下ろした『黙って行かせて』が肉親の情と亀裂、時代と政治的熱狂が母娘の血の絆に切り込む刃の鋭さについて考えさせる沈痛な読書体験だった。
ピンク・トライアングルとは、ナチ強制収容所で同性愛者の刑務服の胸につけられた印である。たぶん、日本人の多くはユダヤ人につけられた黄色いトライアングル印を写真や映画を通しておなじみだろうが、同性愛者にピンク色が強制されたことを知る者は少ないと思う。同性愛者のユダヤ人は黄色とピンクの二つの印を強制された。その二つの印をつけた囚人の映像に記憶がないのは、たぶんガス室に送られる優先順位の筆頭者であったからだろう。ナチズムによる最大の絶滅種、ということになる。
ちなみ赤は政治囚、紫は聖書研究者(エホバの証人)、緑は刑事囚、青は亡命者(ドイツ人及び占領地で捕まったドイツ人亡命者)、茶色はロマ族(ジプシー)であった。刑事囚を除けばナチズムのドグマ的政治システムにおいてのみ「囚人」となった人たちで、もとより拘束されるいわれのない人たちだ。
本書は、ピンク・トライアングルを強制され生き延びた男性の6年の極限状況が簡潔に綴られている。生き延びるため、看守たちに「性具」として自らを差し出したことも隠していない。ホモセクシュアルであるための悪罵・痛罵も克明に記録されている。生きて強制収容所を出る、という最終目標を達成するために手段を選ばないという覚悟は尊い。けれど、読者のなかには、矜持という言葉を持ち出し、恥辱を受ける前に潔い死を向かえよ、と考える人もいるだろう。しかし、そうした恥辱を受け入れなかった者は、その矜持も潔さもガス室で葬られ、自ら報告者となることはできない。極限の餓えを生き延びるため人肉に喰らいついた者はゆるされる。しかし、人肉を喰らうことを拒否して餓死した者も出る。アンデス山中に不時着した飛行機の乗客のなかで、そんな運命の選択が行われた。つい数十年前の現代の記録である。人肉を拒んで餓死した人たちのメ名誉モは、人肉に喰らいついた者たちによって記録されたのだった。そんなことを本書は思い出させる。
生き延びた著者は家に戻り、息子が同性愛者として強制収容所送りとなり、システマチックに職を奪われた父親は生活難と恥辱のなかで死を選んだことを知る。悲劇は解放後も著者を縛った。著者が本書を公けにしたのは1972年、解放から27年目のことだった。心の傷を癒すのに、否疼きのなかで綴ったというべきだろうノノそれだけの歳月を必要としたのだった。人間の悪行と、それに耐えた勇気の記録として推奨したい。
|