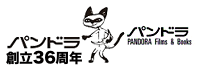|
帯に、「満州映画協会・・・偽の国・満州に造られた文化侵略の工場! その設立から崩壊までを追う迫真の記録!」とある。「迫真」という箇所を除けば、ほぼ本書の内容を言い切り、首肯。昭和史資料としても1級。「満映」に関する資料としては、おそらく山口淑子さんの自伝『李香蘭 私の半生』にならぶ必携文献であろう。
本書を読みきって数日後、中国・上海発のニュースで「『満鉄資料』目録を出版 30万種以上全30巻」という巨きな資料集が中国で刊行されたことを知った。「満映」に関する資料も相当数、あるらしい。邦訳の可能性は今のところ机上にも上っていないようだから、本書の優位性は当分つづくことだろう。
「満映」の設立は1936(昭和11)年、満鉄の進捗状況などを映像記録として残すために設けられていた「映画班」を拡充した満鉄映画製作所に始まる。「映画班」の活動そのものは1923(大正12)年に満鉄に弘報係が設けられたとき、独自の現像所まで設置して総勢20名を擁したというから、その「班」を嚆矢としてもよさそうだ。そういう史実は無論、本書で教えられたことだ。
満州国が「建国」されたのが1932年であるから、満鉄はもとより「映画班」はカイライ国家の成立以前から活動していたことになる。当時の映画制作の困難という状況からすれば「旺盛」ともいえるもので、作品として編集された記録映画も掲示されている。そう、「満映」前史からはじまって、ソ連軍の中国華北地方への侵攻、日本敗戦によって解体した満映から出た中国人たちの「戦後」の消息まで綴った通史である。
冒頭で「迫真」という言葉は少々、語弊があると言った。物語やドキュメントにおける叙述の充実を指して「迫真」というのであって、本書は基本資料に語らせようという実証性を重視する。「迫真」ではなく「真実」の記録というべきだろう、という評者の思いだ。要するに、帯の惹句より評者の方が本書を高く評価しているということである。
本書は多角的・複眼的な読み方が可能だ。その意味でも基本資料として1級なのだ。昭和史、中国近現代史という巨視的な扱いから、カテゴリー化して日本映画史、中国映画史としても活用できる。また、失われたフィルムの貴重な梗概集でもある。そして、なにより重要なことは満映の発足から沿革、人事、機構の細部まで詳細に記され、それが時代の動向と密接に絡み合いながら活動をつづけた文化侵略の構造解明を眼目にしていることだ。
本書と同時に前から気になっていた前掲書『李香蘭』を併読した。
本書の表紙そのものが「満映」の宣伝雑誌『満州映画』の表紙を飾った李香蘭の彩色ポートレートであった。「満映」はスター俳優・李香蘭と、そして理事長として辣腕を振るった甘粕正彦の二人を象徴的な存在として語られてきた。李香蘭の位置が「満映」でどのようなものであったかは、本書では彼女の給与額、社員の給与対照といった具体的な数字で示されている。そういう数字の雄弁性は類書を超える。『李香蘭』では、その高額所得者としての華やかな生活が控えめに叙述されているわけだ。甘粕は周知のように関東大震災の混乱のなかでアナーキスト大杉栄、伊藤野枝、そして一少年を殺害したとされる元憲兵大尉である。
この二人に「満映」が象徴されてしまうのは、スクリーンの華として成功した李香蘭、それを支えた実務家としての甘粕正彦の才能で示されるからだ。しかし、甘粕はあくまで冷徹に意識的にそれを操作し、李香蘭こと山口淑子は無意識に利用され滑稽の無惨と悲劇性が象徴されている。しかし、本書はそうした個々人への傾斜を避けて「満映」という巨大な有機体を俯瞰し、ときに細部へのこだわりをみせる。しかし、特定の人物を摘出して指弾ないしは擁護するような感傷主義に陥っていない点が資料としての信頼性を高める。
山口は戦後、李香蘭であった当時、「満映」に主演した映画を見直し、自分がはからずも中国侵略のお先棒を担ってしまったことを知って映画館のなかで慟哭する描写が半生記『李香蘭』に書かれている。中国を愛したがゆえに身につけた中国語、そして習俗・習慣、そして美貌と歌唱力をもつタレント性豊かな山口淑子という存在は、甘粕らの目には“使える”生きた侵略人形、可塑性の素材であった。そんな自分を真摯に見つめなおしたのが『李香蘭』であり、1級の資料であると同時に、歴史の波頭に否応なく呑み込まれた一女性の物語であった。事実は小説より奇なり、とは『李香蘭』のような書物をいうのだろう。
閑話休題。本書の意義を強調して過ぎることはないように思うが、「満映」の文化侵略の効果が、侵略を受けた中国の映画研究家によって書かれていることも強調しておかねばならない。しかし、その論述は優れて客観的である。教条主義的な日本軍国主義批判といったドグマ性を避けているのは、これが激越な権力抗争であった文革の後に出てきた、つまり闘争の冷却期の仕事であるからだろう。著者は記す、「満映」で働いていたため文革期にいわれない弾圧を受けた人たちがいたこと、ゆえに不遇の生涯を閉じた才能が少なくなかったこと……偏狭な教条主義を身勝手に振りかざす同胞の存在まで記述して筆を止めている著者の真率な客観主義、歴史観に敬意を表したい。
|