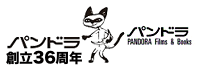『アギーレ/神の怒り』石坂健治さんトークイベントレポート
2022年6月19日(日) アップリンク吉祥寺にて
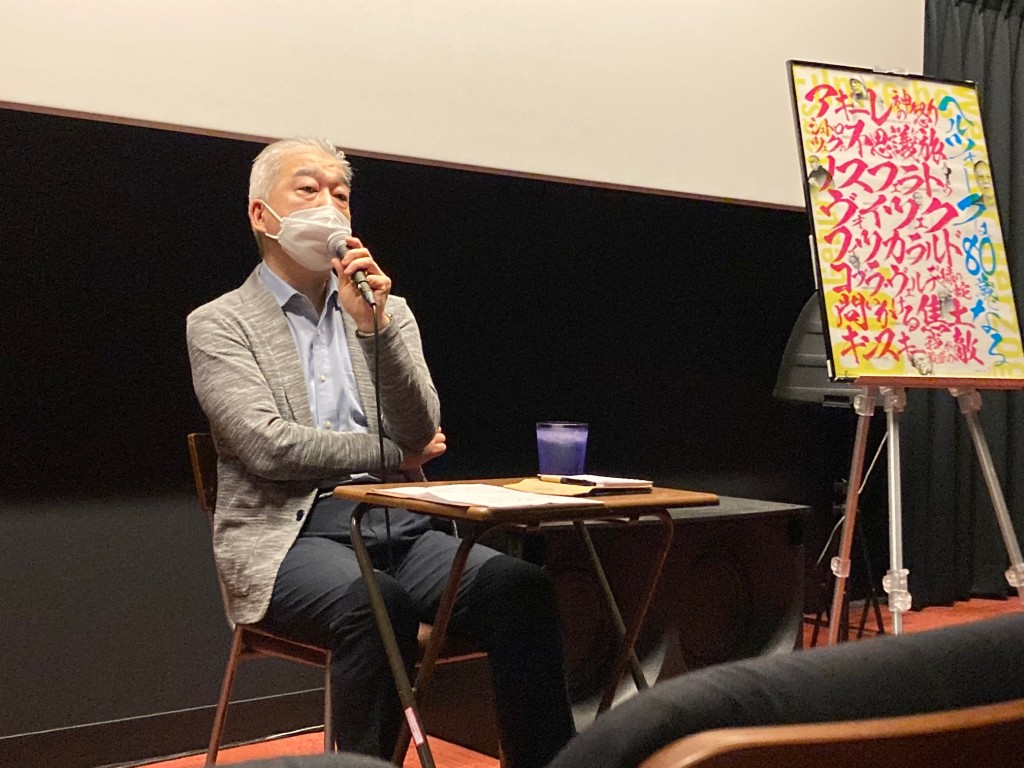
久しぶりに『アギーレ/神の怒り』を見てやはり新しい発見がありました。まずクラウス・キンスキーの強烈さに目を奪われますが、意外と(特に中盤は)あまり何も起こらず、むしろ話が停滞していきますね。ぐるぐると渦巻きに巻き込まれる筏がそれを象徴的に表現していますが、停滞している中でラストに向かい狂気が募っていく構造になっています。ヘルツォークの長編デビュー作『生の証明』(1968年)に近いと思いました。『生の証明』は第二次大戦中、ある島の警備を任された兵隊たちの話です。戦争中だけれども敵が攻めてくるわけでもなく、何も起こらない中で兵士の精神が狂っていくというものです。今日はいくつかキーワードを設定してお話したいと思います。
ヘルツォークとヴェンダース
一つ目はニュー・ジャーマン・シネマ、特にヘルツォークとヴィム・ヴェンダースとの関係です。ニュー・ジャーマン・シネマは公式には1962年、ヘルツォークたちより少し上の世代の作家が集まって、父親の世代との決別を謳いました。「古い映画よ、さようなら」という俗に言うオーバーハウゼン宣言で知られます。オーバーハウゼン宣言から始まってニュー・ジャーマン・シネマのメンバーは色々いますが、生まれた年が一番後だったファスビンダーが、一番早く死んでしまいます。ファスビンダーが亡くなるのが1982年ですから、1962年から1982年までがニュー・ジャーマン・シネマの年代と言われます。第一世代が1930年代生まれのクルーゲ、シュレンドルフやジーバーベルクなどです。第二世代がヘルツォークを含む40年代生まれです(ヘルツォークは1942年生まれ)。ほかにファスビンダー、ヴェンダースなどがいます。フォン・トロッタ、ザンダース=ブラームスといった重要な女性作家も何人かいます。クルーゲのデビュー作『昨日からの別れ』は、まさに彼らの運動をそのまま表したようなタイトルです。でも作家の個性はみんな違います。
- ニュー・ジャーマン・シネマ
1960年代後半から 70年代にかけて興隆したドイツ映画の新しい動き。1962年2月、若い監督たちがいわゆる「オーバーハウゼン宣言」を発表。旧来の映画に「死」を宣告し、因襲的・商業主義的な既存の映画制度に束縛されない新しいドイツ映画を創造すると決意表明した。1965年には運動の中心的人物で理論的指導者でもあったA.クルーゲによって、政府援助による「若いドイツ映画管理委員会」の設置が実現し、非商業映画に対する公的援助システムが確立した。この流れで頭角を現した監督たちが現代ドイツ映画を代表する監督になり、国外にも大きな影響を与えた。 - ヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)
1945年8月14日~。デュッセルドルフ生まれ。ニュー・ジャーマン・シネマの先駆者のひとりであり、現代ドイツを代表する映画監督。『ゴールキーパーの不安』(1971)で長編映画デビュー。ロードムービー三部作『都会のアリス』(1974)、『まわり道』(1975)、『さすらい』(1976)が国際的な注目を浴びる。代表作に『パリ、テキサス』(1984年/カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞)『ベルリン・天使の詩』(1987年/カンヌ国際映画祭監督賞)、『ことの次第』(1982年/ヴェネチア国際映画祭金獅子賞)『ミリオンダラー・ホテル』(2000年/ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞)等多数。写真家としても活動している。 - ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(Rainer Werner Fassbinder)
1945年5月31日~1982年6月10日。西ドイツのバート・ヴェリスホーフェン生まれ。1967年よりミュンヘンの劇場で監督、脚本、俳優業を開始。37歳で急逝するまで16年間で44本の映画、テレビ映画を制作。代表作にカンヌ国際映画祭FIPRESCI賞、エキュメニカル審査員賞受賞の『不安は魂を食いつくす』(1974年)、ベルリン国際映画祭銀熊賞、主演女優賞受賞の『マリア・ブラウンの結婚』(1979年)、ベルリン国際映画際で金熊賞受賞の『ベロニカ・フォスのあこがれ』(1982)等。 - アレクサンダー・クルーゲ(Alexander Kluge)
1932年2月14日~。ドイツ・ザクセン=アンハルト州出身。ニュー・ジャーマン・シネマを代表する一人。テオドール・アドルノ(ドイツの哲学者、社会学者、音楽評論家、作曲家)の社会学研究所の顧問弁護士を務めるなか、アドルノの勧めにより映画研究を始める。1958年、アドルノの仲介でフリッツ・ラングと知り合い助手に。1960年短編映画『石の獣性』(P・シャモニと共同製作)でデビュー、同年のオーバーハウゼン国際短編映画祭で6つの賞に輝く。1962年には「オーバーハウゼン宣言」に参加し、以降「若きドイツ映画」の中心的作家として活躍した。 - フォルカー・シュレンドルフ(Volker Schlöndorff)
1939年3月31日~。ドイツ、ヴィースバーデン生まれ。1956年に一家でフランスに移住。パリで経済学と政治学を学んだ後、高等映画学院に入学。その後、ルイ・マルやジャン=ピエール・メルヴィル、アラン・レネの元で助監督を務めた。1960年、短編“Wen kümmert’s?”で映画監督デビュー。1966年、初長編監督作『テルレスの青春』を発表し第19回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞。1979年、ギュンター・グラスの同名小説を映画化した『ブリキの太鼓』を発表。第32回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール受賞。1980年第52回アカデミー外国語映画賞受賞。 - ハンス=ユルゲン・ジーバーベルク(Hans-Jürgen Syberberg)
1935年12月8日~。ドイツの映画監督。65年に初長編ドキュメンタリー『フリッツ・コイトナー、シラーの「たくらみと恋」を稽古する』、68年初長編劇映画『人間はどれだけの土地が必要か』を監督。1972年『ルートヴィヒII世のためのレクイエム』にはじまる「ドイツ三部作」で、戦後ドイツの歴史意識に挑戦するような耽美的世界としてのナチズムとドイツの関係を描き、ドイツ国内で激しい議論を呼んだ。ジーバーベルクはドイツではアウトサイダーであり続けている一方、アメリカやフランスなど国外での評価は高く、米“The Village Voice”誌で「最も偉大でありながら最も顧みられない現代の映画作家のひとり」と評された。 - マルガレーテ・フォン・トロッタ(Margarethe von Trotta)
1942年2月21日~。父親は画家。ベルリン生まれ。1960年代パリに移り、女優としてファスビンダー監督の『聖なるパン助に注意』や『悪の神々』、シュレンドルフの『ルート・ハルプファスの道徳』などに出演。1978年『第二の目覚め』で単独での長編映画監督デビュー。長編三作目『鉛の時代』で1981年ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞受賞。名実ともにニュー・ジャーマン・シネマの仲間入りを果たす。2018年テオドール・アドルノ賞受賞。 - ヘルマ・サンダース=ブラームス(Helma Sanders-Brahms)
1940年9月20日~2014年5月27日。セルジオ・コルブッチ、ピエル・パオロ・パゾリーニのもとで映画監督としての訓練を受ける。ニュー・ジャーマン・シネマの時期に監督として名をなした。代表作に『ドイツ・青ざめた母』(1980年/第30回ベルリン国際映画祭正式出品)、『クララ・シューマン 愛の協奏曲』(2008年)等。 - 『昨日からの別れ』(原題:Abschied von gestern/1966年/87分)
監督:アレクサンダー・クルーゲ/撮影:エトガル・ライツ トーマス・マウフ/出演:アレクサンドラ・クルーゲ、ハンス・コルテ
東ドイツから単身で西に渡った女性アニタの放浪の日々を、断片的なストーリーとフィクションと記録の融合で描いた作品。
「風景の作家」
ヘルツォークの場合は、『アギーレ/神の怒り』もそうですが、この世ならざる風景、日常ではなかなか見られないような風景がまずあり、そこにドラマをのせていくという、いわば「風景の作家」と言えると思います。この点で比較すると面白いのがヴェンダースです。新しい波ができる時は大体どこの国でも、最初は皆若くてお金もないので、お互いにスタッフをやったりキャストをやったり、お互いに助け合います。これはフランスのヌーヴェルヴァーグがまさにそうですし、台湾ニュー・シネマでもホウ・シャオシェンとエドワード・ヤンは初期にお互いの映画に出ています。ヘルツォークはヴェンダースの1980年代の作品に何本か出ています。印象的なのはヴェンダースの『東京画』(1985年)というドキュメンタリーです。小津安二郎の『東京物語』ゆかりの場所や人を訪ねていくという作品です。この作品で、東京タワーにヴェンダースが登り、ヘルツォークと二人で語り合うのが印象的です。ヘルツォークはそこで「もうこの地球上に撮るべき風景がない」と言います。1983年の撮影だそうですから『アギーレ/神の怒り』も『フィツカラルド』も撮り終わった後です。
ヴェンダースもある意味風景の作家ですが、対照的なのは、ヴェンダースのは人間サイズの風景だということです。小津の痕跡、『東京物語』の記憶、そういったものを探しに東京に来て、結局バブルの真っただ中で、わずか35年前の『東京物語』ももはや神話の世界だと結論付けて帰っていくわけです。そんな作品の中で、ヘルツォークは「いや、俺は月に行く」「もう月面を撮るしかない」というようなことを言っています。ヘルツォークの作品の大半は非欧米圏、いわゆる第三世界が舞台です。『アギーレ/神の怒り』もそうですが、超絶的な風景があり、そこにドラマがのっかりフィクションがつくられる場合と、風景そのものに語らせてドキュメンタリーをつくる、この半々ぐらいで今日まで来ていると言えると思います。
- ヌーヴェルヴァーグ(Nouvelle Vague)
1950代後半から始まったフランス発のムーヴメント。「新しい波」を意味する。当時、20歳代の若い監督らが古い道徳観や撮影所システムに囚われない手法で制作活動に着手。低予算やロケ中心で製作され、刹那的な若者たちの友情・恋愛・犯罪・時代感を切り取りった作品が多い。『死刑台のエレベーター』(1958年/ルイ・マル監督)、『勝手にしやがれ』(1959年/ジャン=リュック・ゴダール監督)、『大人は判ってくれない』(1959年/フランソワ・トリュフォー監督)等意欲作が相次いでつくられた。 - 台湾ニュー・シネマ
1980年代から90年代にかけ台湾の若手映画監督を中心に展開された一連の運動。従来の商業ベースでの映画作りとは一線を画した場所から、台湾社会をより深く掘り下げたテーマの映画作品を生み出そうと多くの作品がつくられた。代表作に、台湾映画界の若手監督4人がメガホンをとり、1960~80年代を背景に子ども時代から青年時代までの4つの物語を手がけた短編オムニバス『光陰的故事』(1982年/監督:タオ・ドゥツェン、エドワード・ヤン、クー・イーチェン)等。 - 『東京画』(1985年/ヴィム・ヴェンダース監督)
ヴェンダース監督が、敬愛する小津安二郎へのオマージュを込めて撮ったドキュメンタリー。1983年4月、東京で開催されたドイツ映画祭のために来日したヴェンダース監督は、小津の描いた“東京”を探して街をさまよい歩く。鎌倉の小津の墓も訪問。監督の好奇心の赴くまま、パチンコや竹の子族など当時の“日本的”風景を記録。小津作品には欠かせない俳優・笠智衆や小津組の名カメラマン・厚田雄春との対話を交えながら、小津の“東京”と、近代化した80年代の東京を描き出す。
クラウス・キンスキーとの「共犯関係」
そしてフィクションを割合頻繁につくっていた時に一緒に組んでいたのが、クラウス・キンスキーです。やはり圧倒的な存在感ですね。今回の上映作品にもある『キンスキー、我が最愛の敵』を観ると、撮っている側と撮られている対象の二人の強烈な共犯関係というか、ヘルツォークのカメラの前でキンスキーが化学反応を起こすかのように感じられます。1970年代から1980年代にかけて5本、監督と主演という関係で撮っています。やはりここがヘルツォークの一つのピークだったと思います。元々、状況が停滞している中で狂気が募っていくような割合静かな映画も作っていたのが、まず風景を探し、それからキンスキーが現れたことで強烈な劇映画5本を一緒につくるということになりました。ですからヘルツォークの場合、キンスキーが現れる前と、キンスキーと一緒につくったものと、その後という三つほどに分けて考えることができると思います。
ポストコロニアルの映画表現
もう一つのキーワードはポストコロニアリズムです。思想でも文学でも映画でもそうですが、植民地支配が終わった後の、負の部分も含めての遺産があります。その植民地体験、植民地時代をどういう風に反省、考察するかという点が、20世紀の後半から一つの文学や思想の流れの中で大きな位置を占めています。ポストコロニアルの映画表現を考えた時に、ヘルツォークは非常に重要な作家だと言えます。『アギーレ/神の怒り』は16世紀、大航海時代の新大陸、南米、現在のペルーが舞台です。マチュピチュの600m下の川が舞台になって話が進んでいきます。ヘルツォークが風景を探していく中で、かつて西洋が支配していた土地を発見した。そこでその場所でドキュメンタリーや劇映画を撮る時に『アギーレ/神の怒り』もそこの先住民、インディオに出演してもらい撮ったということです。『フィツカラルド』もそうですし、『コブラ・ヴェルデ緑の蛇』も扱っている時代は違いますけがそういったつくり方だと思います。
映画の場合、西洋人が植民地時代を描く際の一つのやり方があります。ヘルツォークはその代表例ですが、あえて暴力や狂気を、時代劇の中に入れて強調するやり方です。『アギーレ/神の怒り』を観れば分かると思いますが、強烈な征服者側のキャラクターが出てきて、先住民は簡単に殺されたり、征服者側では仲間割れが起こります。アギーレは、ナンバー2なのか3なのか、最初トップではありませんが、だんだん周りを殺してのし上がっていきます。アギーレは、少し右肩が下がって「リチャード三世」のような障害があるような歩き方をしています。せむしの悪漢で、末っ子で、周りを次々に殺して王様になるというシェイクスピアの戯曲と重なって見えます。この強烈な狂気、暴力を持ってあえて「当時はこうだった」というリアリティを出すやり方。これは西洋側、かつて支配していた側からの一つの描き方です。ベルギーのシャンタル・アケルマンという女性監督の、植民地体験を描いた『オルメイヤーの阿房宮』(2011年)という映画があります。ボルネオに赴任した白人の商人が主人公の、相当な暴力や狂気の中で色んな事件が起きていくという作品です。原作はジョセフ・コンラッドで、『地獄の黙示録』でおなじみの作家です。『地獄の黙示録』もベトナム戦争をアメリカ側から描くという、これも狂気と暴力の世界でした。
- ポストコロニアリズム(Post Colonialism)
西洋による植民地支配(Colonialism)という歴史的事実と、旧植民地が独立したあとの西洋と非西洋の関係、変化のプロセスについて考察し記述する。植民地支配の影響は、政治、経済、歴史のみならず、宗教、文化、芸術、アイデンティティ、人種、ジェンダー、階級など様々な側面から複雑に影響し合っており、植民地主義による支配・被支配の相互関係を読み解くもの、歴史における戦争暴力を問うものなど、領域横断的な取り組みが見られる。「ポスト」という接頭辞は、様々な地域が解放された後、現在もなお植民地主義の影響のもとにあるということを示すために用いられる。 - 「リチャード三世」(1592~93年頃執筆)
イギリスの劇作家シェークスピアによる悲劇・歴史劇。風貌怪異なグロスター公リチャードは王位への野望に憑かれ、戦乱のなかにのみ自己の存在理由を見出し、陰謀と暴虐の限りを尽くす。古い形式のなかに近代的な人間解釈を盛込む。 - シャンタル・アケルマン(Chantal Akerman)
1950年6月6日~。ベルギー・ブリュッセル生まれ。両親はユダヤ人で、母方の祖父母はポーランドの強制収容所で死去。女性でありユダヤ人でありバイセクシャルであった15歳でジャン=リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』を観たことをきっかけに映画の道を志し、18歳の時に自ら主演を務めた短編『街をぶっ飛ばせ』(1968年)を初監督。その後ニューヨークに渡り、初長編監督作『ホテル・モンタレー』(1972年)や『部屋』(1972年)などを手掛ける。25歳で平凡な主婦の日常を描いた3時間を超える『ジャンヌ・ディエルマンブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番』を発表し世界中に衝撃を与えた。 - 『オルメイヤーの阿房宮』(2011年)
『地獄の黙示録』(1979年/フランシス・フォード・コッポラ監督)の原作小説「闇の奥」で知られるイギリスの作家ジョゼフ・コンラッドの同名小説を脚色し映画化。東南アジア奥地の河畔の小屋で暮らす白人男性オルメイヤーは、現地の女性との間に生まれた娘を溺愛している。オルメイヤーは娘を外国人学校に入学させる。 - ジョセフ・コンラッド(Joseph Conrad)
1857年12月3日~1924年8月3日。ロシア領ポーランド生まれ。商船員として世界を航海したのち、1895年作家デビュー。99年「闇の奥」を発表。「密偵」「西欧人の眼に」など、現代にも通じる傑作を数多く遺した。
ヘルツォークの弟子、タヒミックからの返答
面白いのは、ポストコロニアルの風景を、アジアや南米、中東などかつて支配されていた側から描く動きが確実に増えてきていることです。ヘルツォークはその結節点のような人でもあります。ヘルツォークの弟子の中に一人、フィリピンのキドラット・タヒミックという監督がいます。国立フィリピン大学を首席で卒業してからヨーロッパのOECD(経済協力開発機構)で仕事をしたエリートですが、ドロップアウトしてドイツの芸術家のコミューンでヘルツォークに出会いました。タヒミックの妻もドイツ人で、ドイツで結婚しました。タヒミックはヘルツォークから映画を学び、今でもヘルツォークが師匠だと言っています。タヒミックは『カスパー・ハウザーの謎』(1974年)に出演しています。この作品は、狼少年というか野生の少年の話です。文明から隔絶されたところで生きてきた青年が社会に出て、野蛮から文明にどのように移行していくかを描いた旅の話です。サーカスの見世物小屋の場面で、珍しい原住民という役でタヒミックは出ています。フィリピン人のタヒミックが、スペインに支配された南米のインディオという役で出ている、この点も相当面白いです。「このインディオは訳の分からない言葉を話します」というようなことを座長が言うわけです。そこでフィリピンのタガログ語をめちゃくちゃに喋りまくって、笛をずっと鼻で吹き続けるというかなり変な役で出ています。後で調べたらとにかくめちゃくちゃなこと、「馬鹿野郎、死んじまえ」などと言っていることが分かりました。そんなこんなでタヒミックは映画デビューして、フィリピンに帰って『悪夢の香り』(1977年)という映画で監督デビューしました。
彼が最近撮り上げた『500年の航海』(2015年)という作品があります。マゼランの世界一周は1522年です。マゼランは途中で亡くなりますが、それを引き継いで世界一周したのがちょうど500年前なのです。タヒミックの主張は、マゼランが世界一周したのではない、ということです。マゼランが死んだ後も船を動かして世界一周をしたのは、マゼランに雇われたエンリケというマレー半島のマラッカ出身の奴隷でした。『500年の航海』はこのエンリケを主人公にしています。マゼランの話のスピンオフどころではなく、価値観自体をひっくり返し、西洋中心主義をひっくり返すという作品です。
でもよくよく考えてみると、タヒミックは、修業時代ヘルツォークから映画を学び、『カスパー・ハウザーの謎』に出るところからキャリアが始まっているのです。これはポストコロニアル的な映画的な表現で言うとちょうどコインの表と裏のようです。『500年の航海』は『アギーレ/神の怒り』と同じ大航海時代が舞台の話です。タヒミックなりの師匠への返答、恩返しと考えると非常に面白いです。こういった西洋の側からのヘルツォークやあるいはコッポラやアケルマン的なポストコロニアルな表現に対して、逆にこれまで支配されていた側からの表現というものも、タヒミックなどを先駆にして恐らくどんどん出てくるだろうと思います。その両方がぶつかってまた色々議論が起こるのがこれからの流れで、私は非常に注目して見ているところです。
- キドラット・タヒミック(Kidlat Tahimik)1942年~。
フィリピン、バギオ生まれ。アジア・インディペンデント映画の父と呼ばれる。デビュー作『悪夢の香り』(1977年)でベルリン国際映画祭批評家連盟賞を受賞。『悪夢の香り』はフランシス・F・コッポラが激賞し、自らアメリカでの配給も手がけた。フィクションとドキュメンタリーを混在させる斬新な映像話法で描き、笑いのなかに先進国の独善と近代化の裏面を揶揄した同作は、タヒミックの名を一躍世界に広め、後進のアジアの映画作家たちに大きな影響を与えた。日本では1982年の国際交流基金映画祭で初上映された。 - 「マゼランの世界一周」
人類史上初めて地球を一周したとされる航海のこと。スペインによって組織された遠征隊が、1519年、ポルトガル人探検家フェルディナンド・マゼランの指揮の下、西回りでの東アジアへの航路の開拓を目指してセビリアを出発。アメリカ大陸を通過して太平洋を横断し、1522年、スペイン人航海士フアン・セバスティアン・エルカーノにより世界一周の航海が完成された。エルカーノ以下の18名の生還者が単一の航海による史上初の世界一周達成者である。