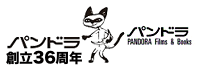『ノスフェラトゥ』須藤健太郎さんトークイベント レポート
2022年7月2日(土)アップリンク吉祥寺にて

みなさま、今日はお越しいただきありがとうございます。と言いつつ、はじめにお断りしておかなければいけないのですが、ぼくはそんなにヘルツォークの作品に親しみがあるわけではなく、彼の映画について詳しい専門家ではありません。「だったらなぜのこのこやって来たんだ」と言われちゃうとつらいのですが、いまご覧になったヴェルナー・ヘルツォーク監督の『ノスフェラトゥ』(1979年)は、もともとフリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウの『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)のリメイクなんですね(ヘルツォーク自身は「リメイク」ではなく「オマージュ」だと言っていますが)。それで、ムルナウの映画は何度も見ているし、ムルナウは心の底から敬愛している監督の一人なので、この二作の比較であれば何かお話しできることがあるのではないかと思って、今日はのこのことやって来ました。
- フリードリヒ・ヴィルヘルム・ムルナウ(Friedrich Wilhelm Murnau)
1888年~1931年。サイレント時代のドイツ表現主義映画を代表する映画監督。『吸血鬼ノスフェラトゥ』以外の監督作に『ジキル博士とハイド氏』(1920年)『ファウスト』(1926年)など多数。
ロッテ・アイスナーのこと
まず、ヘルツォークがこの作品をつくったきっかけからお話しします。ドイツの映画批評家ロッテ・アイスナーという人の存在が大きなきっかけになっています。彼女は1896年生まれですので映画の誕生と同時期に生まれた世代ですが、この1880〜90年代生まれの人たちが1920~30年代に映画芸術の礎を築く世代にあたります。アイスナーは1920年代から撮影現場に赴き、ムルナウをはじめ、フリッツ・ラングなどの監督とも親しくしていた批評家です。しかし、1933年にナチスが政権をとって、彼女はフランスに亡命することになります。すると、今度はパリでアンリ・ラングロワやジョルジュ・フランジュと出会い意気投合し、二人がつくったばかりのシネマテーク・フランセーズという機関に協力し、フランスで批評活動を続けていきます。ラングロワは映画博物館をつくるのが夢でさまざまな資料を集めていたわけですが、その時に大きな力を果たしたのがアイスナーでした。また、ドイツ映画のことをよく知る人がこうしてフランスにやって来たわけです。フランスのヌーヴェル・ヴァーグの作家たちがドイツ映画に親しみがあるとすれば、それはアイスナーがパリにいて、シネマテーク・フランセーズの活動を支えていたおかげなんですね。
彼女は戦後になってから本をいくつか書いていますが、もっともよく知られているのは、まずフランス語で出された『L’Écran démoniaque』(「悪魔に憑かれたスクリーン」とでも訳せますが、英題は『The Haunted Screen』で、こっちのほうが「ホーンテッド・マンション」みたいで覚えやすいですね)。1918〜33年のいわゆるワイマール期のドイツ映画、一般に「ドイツ表現主義」と呼ばれる映画群について書かれた、古典的な名著と言われるものです。なぜか日本語にまだ翻訳されていないので、これはぜひ翻訳してほしい本の一冊です。同時期のドイツ映画について書かれたものというと、ジークフリート・クラカウアーの『カリガリからヒトラーへ』という本が大変知られていて、日本語では二種類も翻訳が出ています。図式的にいえば、クラカウアーはワイマール期に撮られた作品の中にその後にヒトラーが登場してくる集団心理の反映を読み取っていく。『カリガリからヒトラーへ』がある意味ではそういう社会学的な研究だったとすれば、アイスナーの『ホーンテッド・スクリーン』は同じ時代の同じ作品を扱いながら、それを美学的に考察したものというふうに整理できると思います。
ロッテ・アイスナーはこのように映画史家として非常に重要な仕事をした人ですが、それだけではありません。1960~70年代頃に、世界中で新しい映画が出てきましたよね。フランスなら「ヌーヴェル・ヴァーグ」、ドイツであれば「ニュー・ジャーマン・シネマ」というふうに、新しい世代の若い監督たちが登場してきますが、彼女はニュー・ジャーマン・シネマを支えた批評家の一人です。例えばヴィム・ヴェンダース、フォルカー・シュレンドルフ、あるいはヘルツォーク、ほかにもライナー・ヴェルナー・ファスビンダー、人によってはジャン゠マリ・ストローブやダニエル・シュミットなども含める人もいますが、そういう若い監督たちが出てきたとき、彼女はそれを支持した批評家でした。
なかでもヘルツォークはアイスナーのことをとくに慕った若者でした。1974年にアイスナーは病気で倒れてしまい、「もうこれは長くないぞ」ということになったのですが(1896年生まれなので、もう70代の後半でした)、その時、ヘルツォークは「死んでもらっては困る」と、「ちょうど若い監督たちが出てきて映画界が盛り上がってきているのに、いま死なれたら困る」ということで願掛けをするんですね。「ミュンヘンからパリまで徒歩で彼女に会いに行く、これが成功したら彼女は死なない」という願掛けをする。この時につけていた日記はその後に『氷上旅日記』として出版され、日本語にも訳されています。ヘルツォークは願掛けをして冬の寒い中を雪に降られながら、本当にミュンヘンからパリまで歩いて行っちゃうんですね。そしてアイスナーの家まで辿り着くわけですが、そうしたら奇跡的に、「もう死ぬかもしれない」と言われていた80歳近いおばあさんが、死なないんですね。アイスナーは1983年に亡くなりますので、その後9年くらい生きながらえるということが起こります。
ヘルツォークが『ノスフェラトゥ』を撮ったのは1979年です。ヘルツォークは「自分はムルナウの映画にそんなに関心を持ってこなかったが、それを発見させてくれたのはロッテ・アイスナーだ」と言っていますが、なかでも『吸血鬼ノスフェラトゥ』に一番関心を引かれたそうです。彼は『ノスフェラトゥ』をつくった時、アイスナーの先がもう長くはないという自覚があったと思います。ですから、ヘルツォーク自身は「ドイツ映画の歴史的な名作のリメイクをつくることで、自分とドイツ映画史とを結びつける」、「祖父の世代の映画とつながりを持つ」、そういうことがしたかったと言っていますが、もう一方でそういう歴史を発見させてくれたアイスナーに対する最後の感謝の気持ちの表明、彼女に対する感謝を形にしたのがこの作品なんです。
- ロッテ・アイスナー(Lotte Henrietta Eisner)
1896年~1983年。ベルリン生まれの映画批評家。ユダヤ系だったために、33年にフランスに亡命。フランスの映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」等に多くの批評を寄稿。1974年ドイツ映画賞名誉賞、1982年レジオン・ドヌール勲章受章。 - フリッツ・ラング(Friedrich Christian Anton Lang)
1890年~1976年。ユダヤ系オーストリア人映画監督。監督作に『ドクトル・マブゼ』(1922年)『メトロポリス』(1927年)『死刑執行人もまた死す』(1943年)『飾窓の女』(1944年)等多数。 - アンリ・ラングロワ(Henri Langlois)
1914年~1977年。フランスのシネマテーク・フランセーズと映画博物館の創設者。 - ジョルジュ・フランジュ(George Franju)
1912年~1987年。アンリ・ラングロワと共にシネマテーク・フランセーズ創設に尽力した。監督作に『顔のない眼』(1960年)他。 - シネマテーク・フランセーズ(La Cinémathèque française)
映画作品そのものの修復や保存、映画に関する資料等を保存する私設の施設だが、多くの予算がフランスの国から拠出されている。日本の国立映画アーカイブに相当する。 - ヌーヴェル・ヴァーグ(Nouvelle Vague)
1950代後半から始まったフランス発のムーヴメント。「新しい波」を意味する。当時20歳代の若い監督らが古い道徳観や撮影所システムに囚われない手法で制作活動に着手。低予算やロケ中心で製作された。『死刑台のエレベーター』(1958年/ルイ・マル監督)、『勝手にしやがれ』(1959年/ジャン=リュック・ゴダール監督)、『大人は判ってくれない』(1959年/フランソワ・トリュフォー監督)等が知られる。 - ジークフリート・クラカウアー(Siegfried Kracauer)
1889年~1966年。ドイツのジャーナリスト、社会学者、映画学者。ユダヤ人一家に生まれ「フランクフルター・ツァイトゥング」紙編集員として活躍。1933年、ナチス政権の成立に伴いフランスへ亡命。1941年フランスがナチスに占領され渡米。映画書以外に『サラリーマン—ワイマル共和国の黄昏』(1968年)等著書多数。 - ニュー・ジャーマン・シネマ
1960年代後半から 70年代にかけて興隆したドイツ映画の新しい動き。1962年2月、若い監督たちが「オーバーハウゼン宣言」を発表。旧来の映画に「死」を宣告し、因襲的・商業主義的な既存の映画制度に束縛されない新しいドイツ映画を創造すると決意表明した。 - ヴィム・ヴェンダース(Wim Wenders)
1945年~。現代ドイツを代表する映画監督。代表作に『パリ、テキサス』(1984年/カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞)『ベルリン・天使の詩』(1987年/カンヌ国際映画祭監督賞)、等多数。 - フォルカー・シュレンドルフ(Volker Schlöndorff)
1939年~。ヴィースバーデンに生まれるが、17歳のときに一家でフランスに移住。ルイ・マルやジャン゠ピエール・メルヴィル、アラン・レネの下で助監督を務めた。1979年、ギュンター・グラスの同名小説を映画化した『ブリキの太鼓』を発表。第32回カンヌ国際映画祭でパルム・ドール受賞。1980年第52回アカデミー外国語映画賞受賞。 - ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(Rainer Werner Fassbinder)
1945年~1982年。37歳で急逝するまで16年間で44本の映画、テレビ映画を制作。代表作にカンヌ国際映画祭FIPRESCI賞、エキュメニカル審査員賞受賞の『不安は魂を食いつくす』(1974年)、ベルリン国際映画祭銀熊賞、主演女優賞受賞の『マリア・ブラウンの結婚』(1979年)、ベルリン国際映画際金熊賞受賞の『ベロニカ・フォスのあこがれ』(1982)等。 - ジャン゠マリ・ストローブ(Jean-Marie Straub)
1933年~。フランスの映画監督。ダニエル・ユイレ(Danièle Huillet、1936年~2006年)との共同作業で映画を制作し、「ストローブ=ユイレ」として連名標記されることも多い。代表作に『アンナ・マグダレーナ・バッハの日記』等多数。 - ダニエル・シュミット(Daniel Schmid)
1941年~2006年。スイスの映画監督。長編第1作『今宵かぎりは…』(1972年)がルキノ・ヴィスコンティに激賞され、ヴェネツィア国際映画祭で新人監督賞を受賞。独特の虚構世界を構築する映像作家として評価を得る一方、『青髭』や『ルル』などオペラの演出も手掛けた。
ムルナウ版との違い
それで、はじめに予告しておいたムルナウ版との違いなのですが、割と同じなんですよね。人によっては、これは「リメイク」ではなくて「レプリカ」だという人もいるくらいで、基本的に物語はほとんど同じ筋を辿っています。ラストは違いますが、それ以外はほぼ同じ。いくつかのショットは明らかに「真似して撮ってるよね」とわかりますし、画面の構図のレベルでもかなり忠実なリメイクと呼びたくなる、そういう赴きがあります。ただ、同じところが多いということは、逆に違うところを見ていくと、ムルナウとヘルツォークという二人の監督の特徴や作家性の違いが浮き彫りになるような気がします。
では、何が違うか。サイレントがトーキーになっているとか、モノクロがカラーになっているというのはもちろんすごく大きな違いですし、ネズミの数がすごく増えているとか、そういう細かい違いもたくさんあります。ちなみに、いかだの川下りの場面、これはいかにも『アギーレ/神の怒り』(1972年)のヘルツォークによる創作のように思われるかもしれませんが、もともとムルナウ版にあった場面です。ムルナウはいかだを川に浮かべ、船を海に浮かべている。ムルナウ版『ノスフェラトゥ』は山も川も海も全部出てくるという、ロケーションの素晴らしい映画でもありました。
構図はそのまま同じという例を一つだけ挙げます。ノスフェラトゥの乗っている船が街の運河の中に入ってきて、街に到着するシーンがあります。画面の右側からゆっくり船が入って来る、すごい迫力の場面です。この場面もムルナウ版とそっくりそのままなんですが、ムルナウ版だと船がもうちょっと速いんですね。あと、ムルナウは「船が画面に入ってくる。すると、ノスフェラトゥの乗っている船が、背後にある街の教会を覆い隠してしまう」、そういうショットが撮りたくてこれを撮ったんだと思うのですが、ヘルツォークの場合は関心のありかに変化が見られます。ヘルツォーク版だと、「船がゆっくり入ってきて、着岸する」という、船が止まるところをじっくりと撮る。しかも、船長が自分の体をハンドルに括りつけたまま死んでいるわけですけど、船が画面に入ってきて、最後にハンドルに括りつけられた船長の死体が画面に入ってくるまでを撮るわけです。この船長の姿がこのショットの目的なんですね。船が街に入ってくるという描かれる状況も同じで、構図も同じなわけですが、二つのショットでは目的が異なっています。こういう細かな違いは全篇を通して多くあります。
「ノスフェラトゥ」という存在
ムルナウ版とヘルツォーク版でもっとも大きな違いは何かといえば、それは「ノスフェラトゥ」という存在の位置付け方です。ヘルツォークは、「ムルナウのノスフェラトゥは人間味のない怪物みたいな存在だけど、自分のノスフェラトゥはもっと感情があって、愛に飢えていて、人間社会に入りたいと思っているような存在なのだ」という言い方をしていますが、ここで問題にしたいのはそういうことではなくて、「ノスフェラトゥをこの世界の中でどのような存在として位置付けているか」ということです。ヘルツォークとムルナウとでは、これがほとんど真逆といっていいほど違うと思います。
ノスフェラトゥの城がどこにあるかを確認すると、わかりやすいかもしれません。どちらの版でも、誰も連れて行ってくれないので、「じゃあ自分で歩いていきます」ということになって、歩いていきますよね。そうすると、ヘルツォーク版だと秘境探訪みたいな感じで、川がすごい勢いで流れていて、その川沿いの狭い道を通って、なんか水のしたたる洞窟の中に入っていく、というようにして進んでいき、滝みたいになっているところもずっと登っていきます。要するに、川の源流に向かっているわけですね。それで頂上まで登りつめてみると、ワーグナーの『ラインの黄金』のプレリュードが流れます。これは「世界の始まり」を表している音楽だということになっていますから、もうおわかりですよね。ノスフェラトゥの住処というのはどういうところにあるかというと、世界の起源にある、と。川の源流に向かい、その起源のような場所に着くと、世界の始まりの音楽が流れるわけですから、そういうことです。ちなみにこの映画ではもう一回この『ラインの黄金』のプレリュードが流れるのですが、それはノスフェラトゥが街にやって来た時です。彼がやって来ることで、世界は一度滅び、もう一回新しい世界が始まります、ということです。
それに対して、ムルナウ版はどうだったか。ムルナウ版でも誰も連れて行ってくれないので自分で歩いていくわけですが、起源への遡行みたいなことは必要なくて、橋を渡るともう別世界なんです。『吸血鬼ノスフェラトゥ』のフランス語版の字幕でよく知られているものがあって、それは「橋を渡ると、魑魅魍魎たちが迎えにやって来た」というものです。つい「魑魅魍魎」と言ってしまいましたが、これは「les fantômes」なので「亡霊たち」と訳したほうがいいかもしれません。いずれにせよ、『吸血鬼ノスフェラトゥ』は1922年10月にパリで公開されたとき、アンドレ・ブルトンをはじめとしたシュルレアリストたちに熱狂的に迎えられたわけですが、とくにこの字幕が彼らのお気に入りだった。それで、その後にこのフランス語版の字幕が伝説化していったという経緯があります。橋を渡るともう別世界が広がっていて、そこには魑魅魍魎が、亡霊たちが跋扈する世界になっている、と。そういう世界が橋一本隔てただけで、この世界と隣り合っている。ムルナウの映画というのは、基本的に主人公たちがいる世界に対して、それとは別の世界の存在が示され、その別世界から使者がやってきて、こちらの世界の秩序が乱される、だいたい全部そういう話なんですが、その別世界というのはこの世界のすぐ隣にある。
「イメージ」と「身体」
ムルナウの映画で面白いのは、その別の世界がかならず「イメージ」として提示される点です。『吸血鬼ノスフェラトゥ』もそうですよね。ノスフェラトゥという別の世界の住人は「イメージの世界」を体現する存在です。橋を渡ると別世界になり、そこでは亡霊たちが跋扈しているわけですけど、映画ではそれがどう示されるかというと、迎えの馬車はクイックモーションでやって来て、その馬車に乗っていると、白と黒が反転する。いかにも映画的につくられた人工的なイメージの世界として、その別世界は示されます。また、不動産屋で働くフッターがノスフェラトゥの屋敷に滞在するや、なぜか街に残るフッターの妻エレンとノスフェラトゥとが切り返しで撮られ、別々の空間にいるはずの二人があたかも見つめ合っているかのような編集がなされたりもする(妻の名前はムルナウ版だとエレンですが、ヘルツォーク版だとルーシー。名前がなぜ違うかという話も面白いのですが、長くなりそうなので割愛します)。ヘルツォーク版にもあったように、彼女が夢遊病になり、夜寝ていると起き出して歩き出したり、夢にうなされたりするのですが、彼女はどうやらノスフェラトゥに会わずして、彼をヴィジョンとして、幻影として見ているかのようです。ノスフェラトゥがフッター夫妻の対岸の屋敷に移り住むと、その姿が窓越しに捉えられ、あたかも窓枠をフレームとしたタブローのように見せられるのも印象的ですね。彼女はそのヴィジョンに魅了され、最終的には自分の身をそのイメージの世界に捧げ、この世を捨てて、別の世界へと旅立っていきます。
しかし、ムルナウが真に冴え渡っているのは、こっちの世界と別世界があり、こっちの世界が現実で、別世界がイメージの世界として示される、というだけではないところです。こちら側の世界ははじめは現実として与えられていたかもしれませんが、この世界もイメージの世界から見ると、同じように「イメージ」でしかない。いまノスフェラトゥが一種のイメージとして示されているという話をしましたが、ノスフェラトゥからすると、こっちの世界こそがイメージで、彼もまたそのイメージに魅せられる存在なわけです。だから、エレン(ルーシー)は主人公のペンダントの中にある肖像画として与えられる。ノスフェラトゥはそのイメージに魅了され、危険な旅を敢行し、最終的には自滅してしまうことになります。
ムルナウ版ではノスフェラトゥは街にやって来てからは影として映され、その影にエレンは襲われるわけですが、ノスエフェラトゥは朝日を浴びると亡くなってしまう。光が弱点で、ムルナウ版だと本当に朝になって光が差し込んできた途端、ノスフェラトゥは消えてなくなってしまう。ふっと消えちゃうんです。本当に何の実体のない、ただのイメージだったかのように。それに対してヘルツォーク版だとどうかというと、ノスフェラトゥは朝日を浴びて死ぬんですが、消えないんです。死体がごろっと転がっている。実体のないイメージではなく、ちゃんと死体が残る。なので、杭を打ち込んで、ちゃんと殺さなくちゃいけないということになり、杭を打ち込むと、血も出る。ヘルツォーク版のノスフェラトゥはそういう血が通う身体を備えた存在になっている。
ちなみに『ノスフェラトゥ』の原作であるブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』は1897年の刊行で、映画の発明と同時代の作品です。光を浴びると消えてしまう、暗闇の中でしか存在できない。それはあたかも映画館という暗闇の中でしか存在できない、スクリーンの中の存在のようでもあります。ドラキュラとは映画のメタファーではないか、なんていう話もよく語られることですが、ノスフェラトゥを影の存在として示して映画の起源のひとつである影絵を想起させるムルナウは、『吸血鬼ノスフェラトゥ』という映画をつくるときに明確にそういうことを念頭に置いている。その結果、この作品はイメージをめぐるすぐれた寓話に仕上がっています。
ヘルツォークはこういうムルナウ的な問題意識にたぶんまったく関心を払おうとしていない。そこがすごく興味深いところです。ヘルツォーク版の『ノスフェラトゥ』は1979年の作品ですから、VHSが出てくる、MTVが出てくるという時代で、映画が唯一の視聴覚芸術ではなくなり、映像のあり方がそれまで以上に多様化した時代に作られています。ちなみにジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』が1978年で、マイケル・ジャクソンの「スリラー」のミュージック・ビデオが1983年なのですが、ヘルツォーク版『ノスフェラトゥ』はそれらと同時代の作品であることを隠していません。それで、そういう時代になされたムルナウのリメイクだとすれば、つまり「どうやってムルナウ的なイメージの問題を更新していくのか」と、そんな期待をしながらつい見ちゃうのですが、ヘルツォークはそういう問題は扱ってくれないんです。そんな問題は扱わないというのが、彼のリメイクが出した回答だったように思います。ヘルツォークはノスフェラトゥをむしろ世界の起源に位置付け、そこに身体を与え返す。そのあたりに彼の関心があったのではないかと思います。
- ブラム・ストーカー(Abraham Stoker)
1847年~1912年。アイルランド人の小説家。怪奇小説の古典『ドラキュラ』で有名。『ドラキュラ』は吸血鬼ものの定番となった。 - ジョージ・A・ロメロ(George Andrew Romero)
1940年~2017年。米国の映画監督。1978年公開の『ゾンビ』は、以降の「ゾンビ映画」というジャンルを確立したとされる。