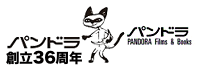|
天使は光を養分として生きているらしい。光の聖性そのものが天使なのだろう。だからカトリック国の画家たちは天使に翼をひらかせ光の満ちる空間に飛翔させた。
けれど、物理学的な光とは別に、光は肉体内部の闇のなかにも生息しているようで、それは繊細な細胞にも染みつき、網膜の内側に潜んでいる。そして、そこにも天使は宿っている、というようなことをヴォルテールは語っていた。
ヴィム・ヴェンダースは『ベルリン・天使の詩』で肉体的実在の天使をみせてくれた。無性無垢の幼子ばかりが、天使の可視化であろうはずがなかった。おびただしい聖像画で強いられた天使のイメージは、ヴェンダースの動画によってたちまち払拭された。それだけでアノ映画は至高の価値を有するものだ。
世に「天使学」というものがあるらしく、その方面の碩学たちが時代の最新の知見を取り入れつつ著した書物によれば、時間と空間を超えて飛翔する天使はカトリシズムの強固な外壁のうちに閉じ込められている存在でないことを知る。「天使体験」といわれるものがある。いわゆる奇跡譚の類い、ともいえる。絶望の淵に立たされた人間を救うナニモノかの存在、いわばケースバイケースで変容する存在としての「天使」を見た、出会ったという体験の累積は膨大なものになるらしい。ローマ法王を輩出したドイツの映画監督が中年の冴えない天使像を造形してみせたのが面白い。その監督ヴェンダースが、宮川一夫さんと淀川長治さんが身体を寄せ合って親しく歓談している様子をみて、「東京の天使」といったそうな。それが、本書の表題に啓示を与えた。けれど、本書の成立には宮川・淀川対談を記録した映画が先行してあって、ついでに……かどうか知らないが、ともかくお二人の全発言が起こされ活字となった。 宮川さんも淀川さんも「映画」を通して、わたしたちに至福をもたらしたという意味においてまさに天使的存在なのだった。この対談当時、すでにお二人とも80歳を過ぎているから老獪な天使である。
淀川さんは映画黎明期からの性根の座ったオタクであり、それが嵩じて映画の宣伝マンへ、ジャーナリストとなった人だから兎にも角にも語りの人なのである。反して宮川さんは明治の職人気質を持った職人肌の人だから自慢げに仕事を語らない。寡黙である。そんなふたりが公衆の前で対談すれば、どうしたって淀川さんの独壇場となってしまう。で、淀川さんは、しきりに「宮川さん、もっと自慢しろ」語れと促しても、宮川さん、最小の言葉で言い切ってしまう。そこでまた淀川さんが、宮川さんの沈黙を補うようにテンションをあげてゆく。淀川さんの語りは雨季の瀑布のようなもので、宮川さんの言葉は瀑布に突き出た動じない巨岩である。そんな対談が臨場感かくもあらんと行間を埋め尽くしている。
正直言って本書は前回、『映像を彫る〜撮影監督宮川一夫の世界』を取り上げた関係で、その補足として読んだ。ゴロ寝しながら読んだ。読んだ、というより接触したという感じでたちまち読了した。淀川さんは映画に投影された人間機微の真実、言葉だけでなく身体表現のささやかな揺らぎのなかで人生一期を刻印できる強さを持つ芸術形式と力説する。批評的な言辞でいえばそういうことである。けど、淀川節はあくまで日常語の世界でそれを語りつくす。
幾度か淀川さんと親しく接する機会をもった。本書の関係でひとつ記しておく。
宮川一夫さんが撮影された映画『曽根崎心中』の完成を祝う小さな会の席だった。淀川さんは、監督の栗崎碧さんを「先生」と言って褒め上げつづけた。けれど、本書を読めば、『曽根崎心中』の成功はまず吉田玉夫さん蓑助さんの至芸があり、人形が生あるもののごとく呼吸するさまを光と影を自在にあつかい映像化した宮川さんの技術があってのことだ、と言外に語っているのだった。でも、淀川長治という人は、主賓がいる席ではけっして、批評しない。すばらしい映画はなにより栗崎碧さんが発案したことによって生まれた傑作に違いないという次元で褒めちぎるのだ。それは確信だから、語尾もあやふやにならない。躊躇を留めるといったはしたないこともしない。だから、日曜洋画劇場の司会でも放映作品をけなさない。いくら駄作であろうが、どこか語るべき美点を取り出して賞賛するウソをつき、平然としていた。テレビの前に座っている視聴者は主賓である。その主賓に向かって、「時間の浪費ですよ」と本音は言えないのだ。ウソをつきつづけてきた、と正直に語るところが淀川さんであって、作り話を真実らしく見せるためのウソをレンズをフィルムに焼き付けたのが宮川さんであった。どちらもウソの名人、ウソも方便ということを知悉した類いまれな天使の歓談が詰まった本がこれである。ということは、堕天使か……。
映画は小さな映写室から放たれた強い光で拡大されて人生、有為転変が語られる。投光に宿る天使が淀川+宮川であった。光を養分にしてわたしたちを楽しませてくれた天使であったのだ。天使angelはギリシャ語起源の言葉から発している。その原意はメッセンジャーであった。つまり、淀川さんも宮川さんも文字通り映画を通してわれわれに慰安をもたらしてくれたメッセンジャーであったのだ。
余談……パンドラで出版されている淀川長治さん関係書は本書だけというので、この連載コラムでは他で書く機会もないようだから、敢えて追記しておきたい。
小生、中学生時代の恥ずかしい話ではある。
実は、淀川長治さんに手紙を書いたのである。
〈将来、映画関係の仕事をしたいと思っているのですが、どうしたら良いでしょう〉といった内容で、主旨明瞭、率直ダイレクト直球の手紙を送りつけたのである。某編集部へ。世間知らずの怖いもの知らずといえばそれまでだが、しかし、中学生の僕はそれなりに「世間」の生き辛さを学んでいたと思う。貧しい家の暮らしと、そして映画を通して。愛に地獄もあれば煉獄もあるということを映画を通してなんとなく理解する童貞であった。こっそりと若松孝二のピンク映画を見れば、東宝特撮モノも溺愛し、日活アクション映画の薄ぺラさより松竹映画を好んだ。桑野みゆき扮するチンピラやくざの情婦が、男にいたぶられ(という言葉はまだ知らなかったが)ても何故、逃げないのか、その不可思議に大人になることの憂鬱を感じていたのかも知れない。マセタいけすかない少年であった。それでも優等生であったし、孝行息子でもあった。こういう少年の心の闇は深く傷つきやすいのである。
淀川さんに書いた手紙には片々たる映画知識をもとに未熟幼稚な評語で書き連ねたものだったろう。返信を本気で期待していたかどうか今となって判然としない。投函からどれくらい経ったのかは覚えていないけど、葉書が来たのである。淀川さんの直筆でギッシリと埋められていた。今でもどこかにあるはずだ。気恥ずかしくて再読できないが、捨て切れずウン十年、引越しの際にも残された。
淀川さんは受け流すことはなく誠実に応えてくれた。〈きみの可能性を今この時期に映画だけに絞り込むのは早すぎるし、未来を自ら狭める年齢でもない〉といった主旨であった。中学生の「野心」を慈しんだ上で書かれた丁重な文章であることが当時の僕にも了解されるものだった。長じて、淀川さんと直接、お話できる場を共有しながら、中学生の無作法を謝辞することはできなかった。僕が中米グァテマラからメキシコへ転居したあわただしい時期、淀川さんは永眠されてしまった。
サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ……。
|