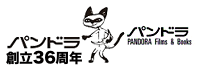「上野清士のBook Talk」 (9) 上野清士
|
ヴェルナー・ヘルツォークの名はボクにとってまず、ナスターシャ・キンスキーの父君クラウス・キンスキーを戦闘的に起用した映画作家として記憶されている、と思う。クラウスのアノ悪魔的面構えの遺伝子が、精管を通して子宮に注入され天の配合によってナスターシャの肉体が創造された。ナスターシャの口元には明らかにクラウスの野卑が刻まれているのだけど、それが彼女にあってはサロメ的な淫蕩さを湛える美となっている。『テス』に主演した頃の話だけど。 その淫蕩は熱帯雨林の底で油照りの光沢をもつ昆虫たちを誘い込む花弁のものでもある。葉切りアリが地を這う密林のなかの花卉類は陰湿だ。旺盛な太陽も樹冠に閉ざされて地にとどかない。ルノアールの輝く色彩とはまったく無縁なところで生来の色相だけを頼りに生を育んでいる。 熱帯雨林の花は生来の色相そのもので生きつづける。熱帯をときに原色の世界というが、その原色とは色相そのものを捕捉するときに正しい。蘭の淫蕩である。ヘルツォークの“熱帯美”はその原色を描き切った見事さにある。ターザンによって熱帯を消費しはじめたハリウッドの「熱帯」が物分り良く親密であったり、いきなりビックリ箱のようにオドロオドロしい裏切りを見せたりするのは精ぜい後期印象派の色彩でしかみていないからだ。ヘルツォークの意匠はドイツ表現主義派の錯綜した破調だ。 ヘルツォークの『アギーレ』『フィツカラルド』、そして『コブラ・ヴェルデ』の主人公たちは……それは皆、クラウスによって演じられるのだが……熱帯を市場経済に組み込もうとしたヨーロッパ人のユダ的欲望が叩き潰される悲喜劇の体現者たちであった。大航海時代に〈新世界〉に乗り出したスペイン軍人たちは皆、一攫千金の野望を「カトリック布教」の衣で覆っていた。クリストバル・コロンの「新世界発見航海」もまたカトリシズムの十字架を重石にした市場開拓建白書「インディアス計画」がイサベラ女王によって認証されて行なわれたものだ。 「発見500周年記念」映画としてコロンの伝記映画が2本撮られたが、その制作者にもっとも相応しいのはヘルツォークであったはずだし、クラウス=コロンで演じられるべきだった。けれど、慶祝行事の誉れから二人はほど遠い。ジェノバの商人コロンの野心は、カトリックの敬虔を装うことで出資者を獲得することができた。コロンの物語は、出港前の権謀の日々のほうが断じて面白い。「新世界」での冒険や征服譚なら、コロンからやや遅れて海を渡ったエルナン・コルテスやピサロの方がずっとスケールが大きく流した血の量は川面を満たすほどだ。コロンの偉大は当時、西欧の版図からイスラム勢力を駆逐して権勢を誇っていたカトリック両王を口先三寸で三艘の外航船を供出させたことにあったはずだ。その旗艦サンタ・マリア号の舳先に立たせる英姿こそクラウスのものだったに違いないし、それを使いこなすのはヘルツォークの蛮力であったはずだ。 筆者に、熱帯生物の営みの豪奢と苛酷、神秘と淫蕩を教えてくれたのは中米ニカラグアの密林で地質調査をしていた鉱山技師にして博物学者のトマス・ベルトであった。かのダーウィンが繰り返し称賛したベルトの仕事だが、それも志なかばにして熱病に冒され中絶する。ヘルツォークが『フィツカラルド』に継いで熱帯を舞台にすべきは、『コブラ・ヴェルデ』の奴隷商人の挫折ではなく、フィツカラルドの足によって絶えず踏みしだかられていた虫の蠢きを観察したベルトの後ろ姿であるべきだった。熱帯生物の過剰こそ“地球の肺”アマゾンの営みを支える根幹であるからだ。 『アギーレ』や『フィツカラルド』を撮った後、ヘルツォークは暴いてはいけない富のあり方を考える。黄金がそこに埋まっていても掘削してはいけない文化の叡智という反合理主義な視点から『緑のアリの夢見るところ』を撮る。 『緑のアリの……』の主張はとてもわかり易い。明々白々である。舞台はオーストラリアのアボリジニ居住区。そのアボリジニが〈緑のアリの夢見るところ〉という聖域の地中にはウラン鉱脈があった。白人の開発会社は大規模開発を目論む。アボリジニはそれを拒む。開発断固阻止! といった肩肘張った姿勢ではなく、日々の祈りの感覚で座り込んでいる。会社に雇われているひとりの地質学者は、アボリジニを説得する合理主義者として登場する。……映画の結末がどのようなものであったか全く忘れている。本書読むと、「謎は謎のまま、映画は終わってしまう」とあったから、忘却して当然であった。 ウランは、人間社会にとって諸刃の剣のような存在だ。生活を快適にする原子力エネルギーを作り出せば、チェルノブイリの破壊ももたらす。『緑のアリの……』は米国スリーマイル島原発事故の5年後、チェルノブイリ原発事故の2年前に公開された。もともと哲学思考に無縁な地質学者がアボリジニと関わるうちに、オレはどうすべきか、と煮え切らない憂鬱をみせてゆく。アボリジニンはきょうもまた気流と対話するようなプリミティブな音楽を演奏して神に祈っている。そんな音を聴いていると鉱山技師も癒されるようだ。といって、彼が開発の是非を問い詰め企業倫理を在り方を問うといった闘士になるわけではない。どっちつかずのまったく曖昧な存在のままでいるだけだ。それは、おそらく筆者自身もふくめて大方の北の人間の怠惰な姿勢そのものであるだろう。ヘルツォーク映画のなかで鉱山技師の存在はすこぶる曖昧な造形のようにみえる。しかし、それは周到に計算されたものだと象徴的存在だと思う。アギーレやフィツカラルドはいわば歴史の寓話のなかで神話化された像であって実態ではないが、鉱山技師は20世紀の実態であった。それこそ20世紀最晩期を生きる文明人の様相に輪郭を与えているのだ。そうヘルツォークからみれば、われわれは鉱山技師のように曖昧なボケた像でしかない、という喝破だった。 そうしてヘルツォーク映画は投了となったはずだ。ふたたび『コブラ・ヴェルデ』のようにヒューマニズムの芽生えの時代に奴隷商人の挫折を描いても書割の物語となってしまう。以後、創作意欲は停滞し退化する。『キンスキー、我が最愛の敵』などは惰性の産物である。そんな仕事は批評家の手に任せおけばよいことなのだ。 熱帯映画の最後となった『コブラ・ヴェルデ』も含め、ヘルツォークの熱帯はプレコロンビア期の文明から隔絶した場に求めている。欧米文明の地にとって僻遠の地というだけでなく、アステカやマヤ、インカ文明の地からも僻地であった。現在も来世紀もおそらく僻地であることが定められたような場所である。ヘルツォークにとっての熱帯はそれだけで一考するに価するのだが、『緑のアリの……』との関連で思い出したことがあった。 ……さて、賢明な読者ならお気づきのことと思うが、拙稿は「書評」として書きはじめたものではない。本書には随分、多くの方が原稿を寄せている。筆者がメキシコに在住していた頃に出た本だから、かなり遅い読者として読んだわけだ。もし、筆者が本書への寄稿を求められたら、徒然なるがままに書いたであろう、というのが本稿である。 (上野清士) |