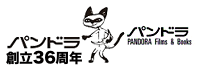ジャーメイン・グリア著『更年期の真実』を訳して 山本博子
| 1992年にイギリス人の友人アンナ・ハーランドからジャーメイン・グリアのTHE CHANGEが話題になっていると聞いた。アンナはウォーリック大学英文学科卒業で、情熱的に文学論を語る30代前半のジャーメイン・グリアの授業を受けていた。 アンナから教えてもらったTHE CHANGEというタイトルからは、更年期の本だということしかわからなかった。今のように、その内容をインターネットで手早く調べることはできなかった。その年の夏、ロンドンの本屋で平積みになっているペンギン版を手にしたときの第一印象は、手ごわく、簡単には読めない本だということだった。 その後、これまで共訳者として仕事をしてきた寺澤恵美子と読み、ジャーメイン・グリアの更年期にたいする姿勢に共感した。だが翻訳となると考え込んでしまった。訳書の「訳者あとがき」に書いたとおりである。 「やってみようか」と始まってしまうのが寺澤と私の仕事のやりかたである。ある意味で、怖いもの知らずである。 こうして始まった翻訳作業だが、寺澤が医学専門書の翻訳の経験者であり、長い間その方面に関心をもっていたことが私にとって救いだった。引用される多数の医学書、そこで使われる医学用語はとても私の手に負えるものではなかった。かつて英文学を専攻した「文学少女」の私は英文学者としてのジャーメイン・グリアに興味をいだいていた。私の場合は本書を文学論の一種のように思いながら、読み、訳していったので翻訳を最後まで続けられたのかもしれない。 ドリス・レッシングの『暮れなずむ女』に更年期女性の経験を読み取るグリアに、読みの深さ、正確さとはどういうものかを教えられる。数多く引用される小説の分析に私がこれまで読んできた小説とその批評の再考を迫られるようであった。 たとえば、ジェーン・オースチンの『エマ』。財産はなく、ごく平凡に、母の世話をしながら暮らしている未婚の中年女性ベイツにたいする主人公エマの無神経な態度を年上のナイトリー(後に、2人は結婚)が非難する。ナイトリーの言葉でエマは自分の思慮のなさに気づき、成長していく。というのがこれまでの批評であった。しかしグリアは、ナイトリーの理屈は「未婚の読者の心に突き刺さり、不安にさせたにちがいない」という。ナイトリーは未婚の高齢者は「これから年をとってゆけば、もっと落ちぶれるだろう」と考えている。グリアは小説の中で道徳的基準となるナイトリーの思想に高齢者女性にたいする固定観念を見抜いている。 ゴードン・バーンの小説『だれかの夫、だれかの息子』のキャサリーンに「起きたこと」は心に残る。これは実際に起きた「ヨークシャの切り裂き魔」事件の小説である。グリアは「中年女性になにも起きないというのは、中年女性が自分たちに起こることを話さないからだ」とキャサリーンの経験を語る。不倫が発覚し、恋人を別れさせられるが、キャサリーンは息子には「ゆっくり死んでいくように思えた」。グリアは、この小説が中年の主婦を主役にするなら何千もの物語を書くことができただろうという。彼女には、語られない多くのことが起きているのだ。読者は次々に女性を殺した恐ろしい息子の物語として読むが、その母親に注目するグリアは私たちに小説を読む時の視点の重要性を教えてくれる。 第1章だけでも、グリアの文学批評の眼を楽しめるが、その他の章でも、ガルシア・マルケス、カレン・ブリクセン、コレットなどの作品の分析に興味は尽きなかった。時には、グリアの分析に異議ありと心の中で叫び、反発し、時には、鋭い視点に感心し、うなずいた。最終章「安らぎとパワー」のエリザベス・ジェニング、エリザベス・ビショップ、エミリー・ディキンソン、スティーヴィー・スミスの詩にたどり着いたとき私自身は、「パワー」が得られたかどうか自信はないが、「安らぎ」に近い気持ちにはなれたと思う。 翻訳作業は苦しく、わからないことでつまずくことも多かったが、共訳者、寺澤恵美子がいなければ、途中であきらめていただろう。スランプのときは2人でビールを飲み、気分転換。(気分転換が多すぎたきらいもある。)翻訳を終わり、1冊の本となり、おしゃれな装丁の『更年期の真実』をみると、二人で翻訳を楽しんだのかもしれないと思ってしまう。こうしてまた次の仕事をはじめてしまうのだろう。 ここに取り上げられた作品の多くを読みたいと思うが、いつになるだろうか。本書の翻訳をしながら、文学の読み方、楽しみ方をグリアから学んだ ・読者の反響から(1) 私はこれは文学書だと思う。さすがジャーメイン・グリア。文章がとても素晴らしい。つまりは翻訳がとてもよくできている。疲れた時にふと手にとって どこから読んでも、ぐいぐい読ませる。日英の女性の差異や文化の相違などを感じさせるけれど、結論がどうのこうの関係なし。たまたま読んだ頁のなかに、時折出てくるポエムのなかに、琴線に響くものが満ちている。更年期は本人にも「不確か」なものだ。私は「もう終わったのか」「まだ続いているのか」よくわからない状態なので、近くに置いて、折りに触れ気のおもむくままに開いてみたい本だ 堅い本なのかと、少しばかり肩に力を入れ読み始めた。表紙の紫色も眼に残ったまま。読んでいくと、とても読み易く、翻訳本とは思えない自然さ、どんどん読み進める。 3年前、3ヶ月看病をしただけで夫をなくしたとき、まだ還暦を迎えていなかった。今、パートナーなどまったく欲しいと思わないし、この3年間一度も思わなかった。この本に出てくる女性たちは、そんな私を異常だと思うのかしらと、考えたり、日本人でも私が少数派なのか、それとも人種の違いによるのか。 ・読者の反響から(2) 私は64歳で更年期のトンネルを抜け出て結構さわやかに過ごしています。といっても、身体の元気さは、やはり60代なりのものになっていますが、それは当たり前だと思っています。前半は少しずつ、後半は一気に読みました。前半部分では更年期の症状が書かれているものと自分の症状が似ていて「そうそう」と頷いて読みました。当時「これは更年期の症状」と思ってみても、病への不安は消えませんでした。こんなこともきちんとしたアドバイスがあれば、不安はやわらぐのにと今は思います。 ・読者の反響から(3) 名前だけしか知らない作家の小説や、その作品を読んだことのある小説家など、パラパラとめくっていて、そこで立ち止まって読むと、新たな発見があり、もう一度その作品を読んでみたいと思う、私にとって好奇心を掻きたてる本です。 更年期障害はあまり感じなくて過ごしましたが、その時期に悩みはありました。産み育て家事をするという役割分担から解放されると、自分の経済基盤を夫に頼っているために、夫との関係が大きな問題となってきました。夫と別れると、とたんに経済的に苦しくなる、かといって、はたらく体力も気力も場所も若い時ほどはない、という問題です。 女性達が、ホルモン補充療法その他の医療にたよったり、異常ともおもえるほど若さを保ちたい気持、また若さが失われたことによる気分の落ち込みの裏には、更年期の身体的変化にともなう精神的影響だけでなく、自分の経済基盤(夫との関係)を確保して置きたいという願いも大きいのではと思うのです。 私にとっては、やはり自分で生きていける経済的基盤と、精神的に自分を支えていく社会の中での役割、社会に対する興味、(社会といっても、ごく限られた仲間うちでの交流でもかまわない)——そういうものがとても大切で、それが一応の目処がついて、今少し落ち着いています。 今日、男性の更年期も話題になるようになりました。彼らにとっても社会的役割の喪失は大きいと思います。 また、男性も女性も、更年期には、更年期独特の悩みと同時に、老いや死の問題もでてきます。自分のために使える時間を持てる時になったから、興味や趣味に時間を使いたいと思う一方で、いつかはそれができなくなるときが来ることも感じるのです。 更年期は、女性(最近は男性も)にとって、身体的変化による、性的な役割の変化を含む大きな人生の節目です。歴史的にも、場所的にも、色々な様相を呈しながら、女性はそれを乗り越えたり、乗り越えるのに失敗したり、またその時を遅らせるために努力の限りをつくしたりします。その様を色々な文献をもとに、示した後で、著者は、それぞれが更年期の後にくる老年期と死を、男性の目から解放され、他人の目からも解放され、自分のものとして、いかに豊かでかけがえのない時として受け入れることができるかという問いを、読者に投げかけているのでは? トルストイの妻に対する態度に怒りを覚え、ボーヴォワールの性愛に対する依存、老いに対する恐怖(7章)には、半ば失望を感じてしまうのですが、彼らにもその生きてきた時代の制約、偏見があっただろうとこの本を読んでいて思いますし、それを知ることによって、自分の置かれている位置をもう一度見直すこともできます。その意味で、更年期の苦しみの中にいる人たちにぜひ読んでもらいたいと思いますが、彼らにはその余裕がないかもしれません。 老いに対するもやもやした恐怖を感じたら、それをもう一度見直すために、時々この本を開きたいと思います。知的刺激を受けたり、考えるヒントをもらったり、それぞれの置かれた状況で普通に歳をとり、いずれ来る死のときを迎えることを考えたりしたいと思います。幸いにも、私が興味を持っている女性のこれまでの生き方、これからの生き方についての参考文献がたくさん、引用文献として、巻末に挙げてあるので便利です。著者は、私の少し先輩にあたる年齢ですが、すごいですね。 実はこの英文の本は我が家の本棚に10年ほど積んでありました。翻訳が出て、日本語で読めるのがありがたいです。膨大な内容と格闘してくださった翻訳者お二人の努力と熱意に深く感謝しています。 。 |