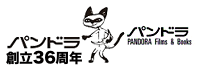|
『アシク・ケリプ』というおまじないの呪文のようなタイトルを持つ映画がある。旧ソ連時代のコーカサス地方、稀代の反骨者たちがよってたかって摩訶不思議な映像美を造型し、モスクワの官僚どもを目くらました。
アルメニアの伝説的な詩人の生涯をコーカサスの民族歴史の輻輳(ふくそう)の綾として描き出した映画だった。セルゲイ・パラジャーノフ監督の豪奢過剰な反吐が出そうな色彩の横溢と、そのただならぬ映像にいささかもたじろがないスコアを提供していたのがジャヴァンシル・クリエフであった。肉厚血のしたたる音響世界であった。
美術の世界では、空間をぎっしり埋める様式をオロール・バクイという。元もと心理学から出てきたラテン語起源の言葉だが、人間の虚無や空白に対して抱く恐怖心を語るものだ。水墨や禅画の空間、セザンヌの余白などと対極にある様式をいうものだけど、パラジャーノフ監督の映像も、クリエフの音楽もオロール・バクイそのものだ。といってそれは恐怖心から出たものでなく表現欲求の当然の帰結として生じたものだ。これと同じような芸術的達成が中米ホンジュラスのマヤ遺跡コパンの神殿内庭に林立するステラ(石碑)にある。
白石さんの詩的イマジネーションに富んだ映画評を筆者は、中米コスタ・リカ在住の友人から送られてきた珈琲を飲みながら琥珀色の空間のなかで味わっていたのだった。部屋はむろんクリエフの触覚的な音で満ちている。
『手帖』というのだから、これは私的なものだ。私的な感想、感興しか綴られていない。啓蒙しようとか観客動員に一役受け持とうというような地点からポ〜ンとシャガールの花嫁のように浮きあがて、詩人が分かち合える少数の友人に、「ネェねぇ凄い映画、見てしまったのよ。ちょっと耳を貸しなさいよ」と熱い吐息が吹きかけられるような感想、それが琥珀の『手帖』。白石さんは筆者とおなじ闇に親しめる禽獣であるらしい。だから会うのが恐そうだ。共喰いをしそうで……。
パラジャーノフ監督はアルメニアの人。
この国の首都はエレヴァン。曇天でもなければ街の南東方向に霊峰アララットの頂きは言うに及ばず優雅な稜線まではるかに見通せる。日本人が富士山を畏敬するように、アルメニアの人はアララットを敬愛してやまない。けれど、その霊峰は国境の向こうトルコ領内にある。まったく手の届かない、はるかな異郷に聳え立つ山をわが胸に染み入る富岳として受け止めている。アルメニアがかつて隆盛を誇っていた古(いにしえ)、アララットは勢力版図の象徴であったのだ。オスマン・トルコに蹂躙され霊峰を奪われたが、民族の記憶までは奪えない。トルコにあってアララットはいまだにアルメニアの心性が占拠するものなのだ。
エレヴァンの無骨な国家宮殿前には広大な中央広場があって、要塞のような国立美術館が四隅の一辺を占めている。その空間はまったくロシア・アヴァンギャルドの色気も香気も清涼も野心も想像精神もすべてスターリンによって毀損された後の無惨を象徴している。硬直した鋭角が幾層にも迫り出している。
パラジャーノフの映像には鋭角は存在しない。人間以外の生物の営みは大抵ぜんぶ曲線空間のなかで終始するのだから、私の映画はスクリーンの四隅の鋭角だけで充分、と主張しているようだ。
白石かずこ、という詩人が偏愛する映画は、パラジャーノフのように自己の表現欲求にあまりに忠実なため、ハリウッド的手法なんててんで眼中にない映像作家たちの私的ないしは詩的営為。CG全盛のハリウッド映画の壮大はサーカス小屋の資本主義的拡大だが、白石偏愛の映画は内的必然の奔放自在のエスプリに満ちた神がかり的解放である。
ノアの箱舟は地上の動物を一つがい選んで乗せたタイムカプセルだったが、『手帖』の映画は、巫女たる白石が水没から救おうと厳選して書き留められた珠玉なのであった。パラジャーノフにはじまって、エミール・クストリッツァ、タル・ベーラ、ジョン・グレイソン、ショーン・マサイアス、ルイ・グエッラ、マルレーン・ゴリス、アウレリオ・グリマルディ、ミラ・ナイール、アレハンドロ・ホドフスキー、シモン・ギャンチョン、ビョン・ヨンジュ、アレクサンドル・ソクーロフ、ドン・アスカリアン、ドゥシャン・ハナーク、ポール・ルデュク、アッパス・キアロスタミ、テオ・アンゲロブロス……琥珀の『手帖』に記された白石の「よき人たち」である。あえて国籍は記さない。国境など「よき人たち」にとっては超脱すべきポリティカルな存在であるからだ。
|